収益物件の出口戦略を考えた投資プランとは?成功のポイントを解説
不動産投資においては、「買い時」だけでなく「売り時(出口戦略)」が成功のカギであると考えられています。不動産は流動性が低い資産なので、売却するタイミングや売却方法を考慮しなければなりません。誤った売却方法を選択すると、大きな損失が出てしまう恐れもあります。
本記事では、収益物件の出口戦略の考え方や種類、投資成功における重要なポイントを分かりやすく解説します。
不動産投資における出口戦略とは?

不動産投資における出口戦略とは、不動産投資を切り上げる方法やタイミングを考え、いかに高く売却するかの作戦を練ることです。つまり、購入した収益物件を将来的にどのように売却し、最終的な利益を確定させるかという「売却に向けたプラン」を指します。
目先の利益だけを考えて「とりあえず買っておく」「利益が出そうなタイミングで売ればいい」といった甘い考えでは、大きな損失を招くリスクが高まります。
不動産投資の世界では、投資用不動産を長期間保有して、インカムゲインを重視する戦略があるのも事実です。しかし、あらかじめ出口戦略を立てておき、売却する方法やタイミング、誰をターゲットにするのかを事前に計画しておくことは、利益の最大化につながります。
出口戦略が不動産投資の成否を決めるといっても過言ではありません。
不動産投資に興味のある方は、ハウスウェルに相談しませんか?お問い合わせはこちら
出口戦略の種類

不動産投資における出口戦略には、いくつかのパターンがあります。それぞれの特徴をみていきましょう。
①収益物件のまま売却する
収益物件のまま売却する方法は、物件の所有者であるオーナーが変わるため「オーナーチェンジ」とも呼ばれています。入居者の立ち退きが発生せず、新しいオーナーもすぐに運用できるため、売却する側も購入する側も手間がかからない点が大きなメリットです。
収益性の高い物件であれば高値で取引できる可能性がありますが、収益性が低い物件の場合は、希望している価格で売却できない恐れもあります。少しでも高値で売却したい方は、保有期間中に「高い家賃で入居者を入れ込む」、そして「少しでも入居率を高める」ことに注力しましょう。
②更地にして売却する
建物の老朽化が進んでいるなら、更地にしてから売却する方法も選択肢の一つです。区分マンションのように他のオーナーがいる場合は現実的ではないため、戸建てや一棟アパートを売却する際に使える手段といえます。
建物の解体費用はかかるものの、前面道路が広い土地や前面道路と接する間口が広い土地など立地条件が良い場合は、住宅用地として高値で売却できる可能性があります。ただし、入居者がいる場合には退去に向けた交渉を行うか、もしくは定期借家として契約して入居してもらわなければなりません。
③自己居住用として売却する
区分マンションや戸建て物件の場合は、購入者が住むための自己居住用として売却するのも一つの選択肢です。
立地や設備などによっては、収益物件のまま売却するよりも高値で取引できるケースもあります。特に都市部の区分マンションは、単身者やファミリー世帯からも人気が高いでしょう。ただし、間取りや立地条件によっては、需要がない恐れもあります。
所有する投資用不動産と似た物件で、過去に自己居住用としての売買の成約事例が多いようなら、この方法での売却を検討してみましょう。
出口戦略を立てるタイミング

出口戦略については、「物件を購入する前」によく検討しましょう。不動産投資初心者のなかには、利回りだけに注目して物件を選ぶ方も少なくありません。しかし、利回りを考えただけでは、売却する際に苦労する恐れがあります。
不動産を購入する前に「将来的に売却しやすい立地であるか」「資産価値が下がりにくい構造であるか」などをチェックすることが、出口戦略を成功させるポイントです。
不動産購入時に出口戦略の視点を持つことで、売却時にも利益を出しやすい投資につながるでしょう。
不動産投資にまつわるお悩みはハウスウェルにお任せください!お問い合わせはこちら
売却するタイミングはいつがベスト?

収益物件の売却で利益を最大化するためには「タイミング」が重要です。ここでは、3つの代表的なベストタイミングを紹介しましょう。
①譲渡所得税が下がるタイミング
個人所有の不動産を売却して利益を得る場合は、「譲渡所得税」が発生します。
譲渡所得税は、不動産の所有期間によって以下のように異なります。
| 種類 | 税率 |
| 長期譲渡所得(所有期間が5年超) | 所得税:15% 住民税:5% |
| 短期譲渡所得(所有期間が5年以下) | 所得税:30% 住民税:9% |
※2037年まで、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を併せて納付する必要あり
このように、保有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」として税率が下がり、課税額に2倍近くの差が生まれます。出口戦略としては、長期譲渡所得に切り替わったタイミングで売却するのがおすすめです。
②減価償却が終了するタイミング
不動産投資において、建物の減価償却が終了するタイミングは、出口戦略を検討する上で重要なポイントです。
減価償却とは、設備投資などの費用を法定耐用年数にわたって計上し、数年かけて資産価値を減少させていく会計処理のことです。減価償却費を経費として計上することで課税所得を抑えられるため、所得税や住民税などの節税につながります。
ただし、減価償却が終了してしまうと、経費計上による節税効果がなくなって課税所得が増加し、キャッシュフローに悪影響を及ぼす恐れがある点に注意が必要です。
建物の法定耐用年数は、建物の構造によって次のように異なります。
| 建物の構造 | 法定耐用年数 |
| 木造 | 22年 |
| 軽量鉄骨(厚み3mm以下) | 19年 |
| 軽量鉄骨(厚み3mm超~4mm以下) | 27年 |
| 鉄筋コンクリート(RC造) | 47年 |
木造や軽量鉄骨のように耐用年数が短く設定されている物件は、減価償却が早く終了してしまいます。例えば、木造アパートを新築で取得した場合、減価償却費を22年間は経費として計上できますが、23年目以降は計上できなくなるのです。
減価償却が終了するタイミングで売却することで、節税効果を最大限に活用し、投資効率を高められるでしょう。
③デッドクロスが近づいてきたタイミング
「デッドクロス」とは、ローンの元金返済額が減価償却費を上回った状態のことです。
投資用不動産においては、法定耐用年数が過ぎると減価償却費を計上できなくなります。また、ローンの利息分は経費として計上できるものの、ローンの元金は経費とすることができません。
デッドクロスの状態になってしまうと、帳簿上は黒字で利益が増えているにもかかわらず、手元に残るキャッシュは減ってしまう現象が起こり得ます。デッドクロスのタイミングが訪れる前に売却することで、損失を最小限に抑えられるでしょう。
まとめ

不動産投資の出口戦略の重要性や、代表的な売却方法を詳しく解説しました。不動産投資で成功するためには、出口戦略をどのように描くかが重要です。利益が確定するタイミングを事前に考え、利益の最大化に向けた対策を検討しておきましょう。
不動産投資に興味のある方は、ぜひハウスウェルにご相談ください。ご予算に合わせた投資用物件の紹介から、リフォーム・リノベーションのプランの提案・施工まで、ワンストップでサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
信頼できる不動産会社をお探しの方は、ハウスウェルにお任せください!ぜひご覧ください
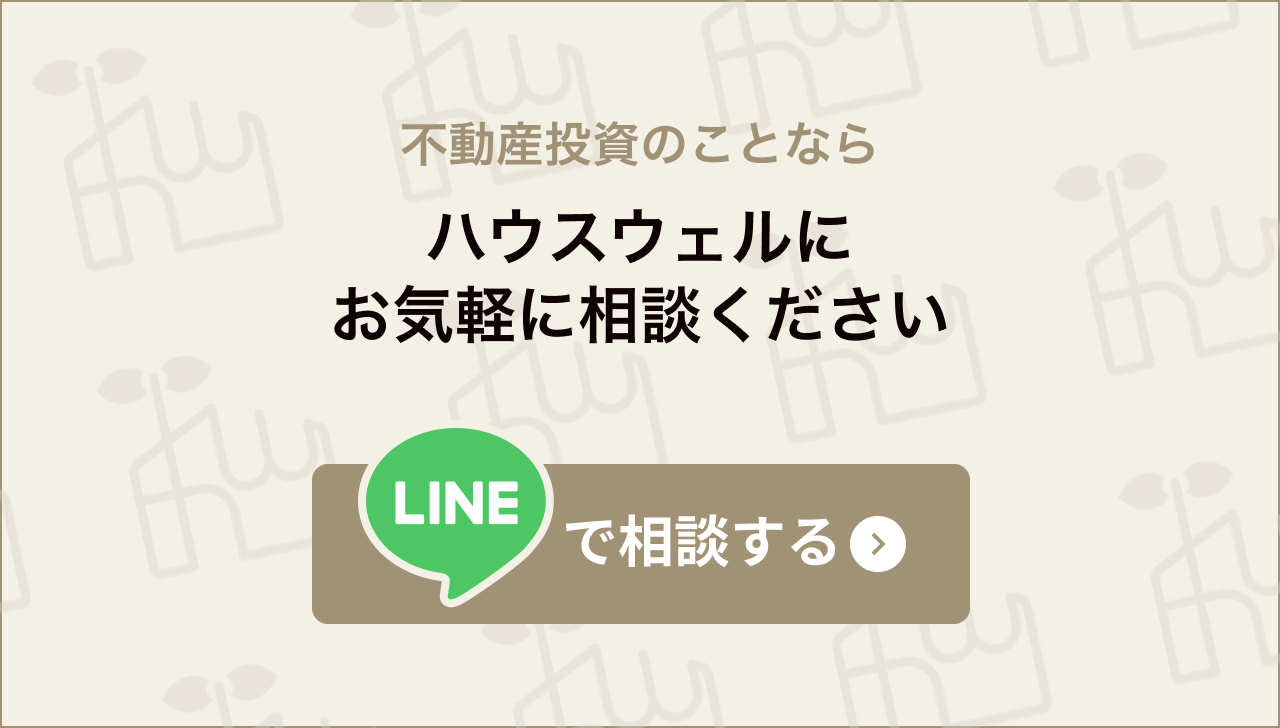 記事一覧へ戻る
記事一覧へ戻る
