不動産投資の減価償却費で節税できる?仕組みと計算方法を解説
不動産投資の減価償却費を活用すれば、年間の所得税や住民税などの税金が軽減できるケースがあります。本記事では、不動産投資における減価償却費の概要や節税に効果がある理由、具体的な計算方法を詳しく解説します。
1.不動産投資は節税につながる?

所得が高く、所得税や住民税の支出が大きくなってしまう人たちに注目されている節税方法として、不動産投資があります。
不動産投資とは、マンションやアパート、一戸建てなどのオーナーとなり、部屋を貸し出したり不動産を売却したりして利益を得る投資方法です。入居者がいる限り、安定した収入を得られるだけでなく、節税効果が期待できるというメリットがあります。
不動産投資を検討している人は、ハウスウェルに相談しませんか?お問い合わせはこちら
2.不動産投資で節税できる仕組み

不動産投資が節税対策になる大きな理由は、減価償却が使えることです。「減価償却」は、所得税や住民税の節税対策に効果的です。
減価償却とは、何年も使えて価格が大きなモノについて、何年かに分けて費用を計上していこうという考え方です。つまり、実際には購入時にまとまった金額で支払った購入費用を、次年度以降の一定期間にわたって少しずつ経費に計上できます。
減価償却によって、不動産購入時から耐用年数が経過するまでの期間中は所得を少なく申告できるため、所得税と住民税を軽減することが可能です。
3.不動産投資の減価償却費とは

不動産投資における減価償却の特徴は、次のとおりです。
| ・建物が減価償却の対象である ・税務上の耐用年数によって減価償却費は変動する |
それぞれの内容を分かりやすく解説します。
①建物が減価償却の対象である
資産と一言でいっても、減価償却できる資産と減価償却できない資産が存在します。
減価償却は、時間が経過したり、使用し続けたりすることで価値が目減りする資産に対してのみ適用されるものです。そのため、建物は減価償却ができますが、経年によって価値が下がっていくものではない土地は減価償却の対象になりません。
建物のように減価償却できる固定資産を「減価償却資産」といい、減価償却によって計上される費用を「減価償却費」といいます。
また、土地のように減価償却できない固定資産を「非減価償却資産」といいます。
②税務上の耐用年数によって減価償却費は変動する
不動産の減価償却を考える上で重要なのが、建物の耐用年数です。減価償却費は、使用できる期間である耐用年数に応じて計上できます。
耐用年数別の償却率は記事の後半でご紹介しますので、参考にしてください。
減価償却費の計算方法

不動産投資における減価償却費の計算方法には、定額法が採用されています。定額法とは、固定資産の耐用年数の期間、毎年同じ額の減価償却費を計上する方法です。
減価償却費の計算式は、次のとおりです。
| 1年間に計上する減価償却費=建物価格×定額法の償却率 |
定額法では毎年同じ金額の減価償却費を支払うことになるため、初期の節税効果が高くなるというメリットがあります。また、毎年同じ額を計上するので、帳簿をつけやすいことも利点といえるでしょう。
参照:No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|国税庁
減価償却費の計算は、以下の手順で行います。
| 1.土地の価格と建物の価格を分ける 2.建物附属設備を分ける 3.法定耐用年数を確認する 4.残存耐用年数を確認する |
土地は減価償却の対象外のため、建物の価格と明確に分けて考えなければなりません。不動産を購入した際の契約書や譲渡対価証明書をチェックし、土地と建物の価格を把握しましょう。
また、建物と設備の耐用年数は異なります。エアコンや照明などの建物附属設備は分けて、別途経費として計上しなければなりません。
建物の耐用年数は、建物の構造によって次のように異なります。代表的な構造ごとの法定耐用年数と償却率は、次のとおりです。
| 構造 | 法定耐用年数 | 償却率 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 | 0.022 |
| 鉄骨造 | 34年 | 0.030 |
| 軽量鉄骨造 | 19年 | 0.053 |
| 木造 | 22年 | 0.046 |
以上を踏まえて「建物価格×定額法の償却率」で減価償却費を算出したら、耐用年数が終わるまで毎年計上しましょう。
なお、中古物件を購入した場合は、残存耐用年数を次の計算式で求めます。
| 法定耐用年数の全てが経過した資産:法定耐用年数×0.2 法定耐用年数の一部が経過した資産:(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2) |
上記で算出された残存耐用年数分だけ、減価償却が可能です。もし経過年数の端数がある場合は、切り捨てて計算してください。中古物件を購入して不動産投資をする際は、残存耐用年数もチェックした上で決断しましょう。
不動産投資に興味がある人は、ハウスウェルに相談してください!お問い合わせはこちら
減価償却を利用して節税する際の注意点

減価償却費は節税に効果的なものですが、次のポイントに気を付けてください。
| ・デッドクロスに注意が必要である ・売却時の譲渡税が高くなるケースがある |
それぞれのポイントを分かりやすく解説します。
①デッドクロスに注意が必要である
デッドクロスとは、ローンの元金返済額が減価償却費を上回る状態を指す言葉です。デッドクロスに陥ると、帳簿上は利益が出ていたとしても、利益に対して課される所得税額が増えるため資金繰りが悪化してしまいます。
築年数の古い物件を購入した場合、初期は減価償却費を大きくとれて帳簿上の利益を圧縮することが可能です。しかし、短期間で減価償却を終えてしまうので、減価償却後はデッドクロスが起こりやすくなります。
節税目的で投資をする際は、減価償却期間が終了するタイミングで売却することも検討しましょう。
②売却時の譲渡税が高くなるケースがある
不動産投資で減価償却を行うと、売却時にかかる譲渡税が高額になる恐れがあります。これは、減価償却を行うたびに、物件の会計上の価値である「簿価」が低くなるためです。
建物の売却価格と最終的な簿価の差が売却益となって、譲渡税を課されます。物件を売却するまでに譲渡税以上の節税効果が期待できない場合は、大きな損失につながりかねないため注意が必要です。
まとめ

不動産投資における減価償却は、一定期間内で分割して経費を計上できるため、節税に有効な方法です。減価償却費を上手に活用することで、帳簿上の利益を抑えて税金の負担額を軽減できるでしょう。
不動産投資を成功させるためには、効果的な節税対策を提案してくれる不動産会社と連携していくことが重要です。
不動産投資を検討している人は、ぜひハウスウェルまでご相談ください。ハウスウェルは、埼玉県を中心にサービスを展開している不動産会社です、不動産売買をはじめ不動産投資にも力を入れており、豊富な実績を誇ります。
お客様の不動産の価値を最大限引き上げ、スムーズな取引をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
信頼できる不動産会社をお探しの方は、ハウスウェルにお任せください!ぜひご覧ください
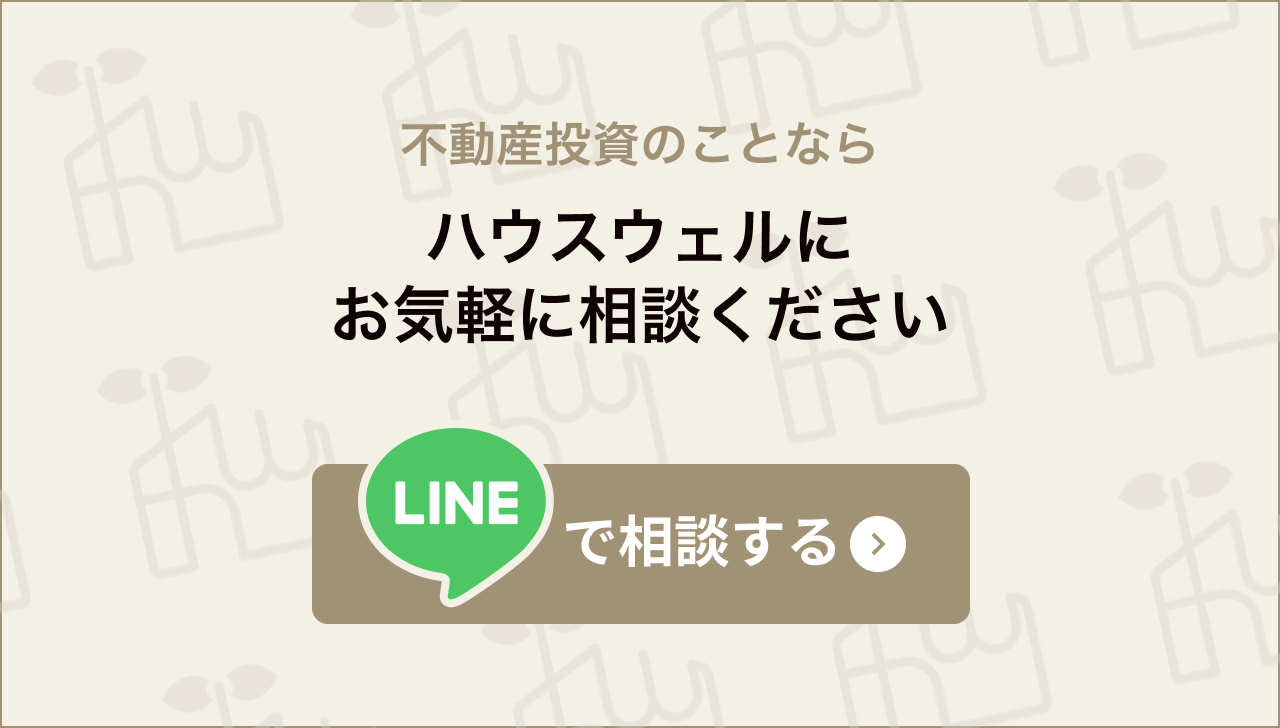 記事一覧へ戻る
記事一覧へ戻る
